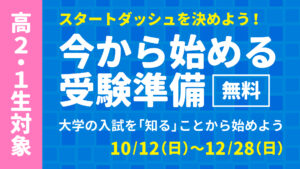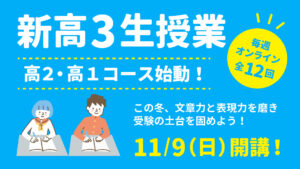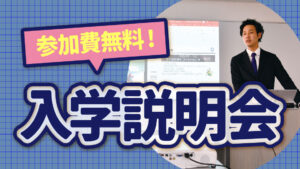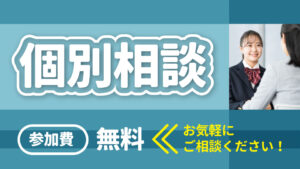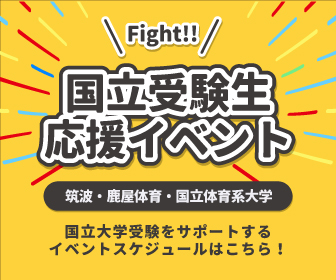本校の土方です。
だいぶ涼しくなりました。9月の10日頃、大雨があって、その後すっかり涼しくなったという記憶があったので調べてみると、やはりその通りでした。9月11日には秋雨前線が南下し、南から湿った空気が流れ込んで、東京都心や神奈川県で1時間に100mmを超える記録的短時間大雨が相次いだ―確かにそうでした。東京の目黒川には氾濫危険情報も発表され、浸水被害があったというニュースは、長年お世話になっている歯医者さんが五反田の目黒川沿いにあるのではっきり覚えています。
涼しくはなったのですが、なんか突如ぱっと秋になってしまったという感じで、何か実感がないといいますか、秋らしいしみじみとした情緒が感じられない。なんだか、庭からは秋の虫の声もあまり聞こえてこないような感じですし、金木犀の花の匂いを嗅ぐと「秋だなあ」と毎年思うのですが、今年はまだ咲いていないし、蕾も少ない。
食欲の秋と言いますから、食べ物で秋らしさを感じられたらいいのですが、それもない。私は栗が好物なのですが、今年は猛暑のせいで不作らしく、スーパーで見かけても、出来の悪さが一目でわかるほど。無論買わず食わずです。
気候変動によって、昔ながらの季節の味わいが失せてきている。頭が変になりそうなくらいバカみたいに暑い夏が長く続いて、突然ポンと涼しい秋になる。ここ数年「気候変動によって日本の四季の構造や情緒が変化・喪失しつつある」という報告や指摘が増えていそうですが、当然かと思います。特に夏の長期化と春・秋の短縮化が顕著らしく、文化的・感覚的な季節感の変容が問題視されているそうです。
味気ない秋の訪れだなあ。そう思っていましたが、先週の休日に「小さな秋」を見つけました。
休日といっても仕事です(笑)。小論文と面接の授業を担当している日体大保健医療学部の学部別選考方式の試験が10月18日にあるので(基礎学力方式は翌19日)、小論文の添削をしたり、予想問題を作ったり、前に作成したものを作り直したりしていました。
仕事がひと段落ついて、一服しに庭に出て、紫煙をくゆらせながら、庭木に水をやっていました。視界を小さな赤いものがさっと飛び過ぎたので行った方を見ると、水道の脇に生えているトクサの上に赤とんぼ1匹が止まっていました。
「赤とんぼ」と言うのは、特定の種類のトンボの名前を指しているのではなく、赤いとんぼの総称で、様々な種類が含まれています。調べてみると日本にいる赤とんぼは約20種類もあるそうです。その中で一番名が知られているのはおそらくアキアカネでしょう。(国民的童謡「赤とんぼ」に歌われているのはアキアカネと言われています。ですが、ウスバキトンボだという説もあるそうで、定かでありません。)私が「赤とんぼ」と言われて、姿と名前が完全に一致しているのはこのアキアカネくらいです。目の前にいる赤とんぼはアキアカネと違い、翅の先端がこげ茶になっていました。(のちに記憶を頼りに調べた結果、おそらくこれはアカネ属のコノシメトンボだと思います。)

私は子供の頃トンボを見つけると、トンボの目の前で指をゆっくりとくるくる回して捕まえるのが好きでした。なぜかゆっくり指を回すとトンボは動きが鈍くなり、捕まえやすいのです。笑われてしまうかもしれませんが、55歳になった今でも周りに人がいなければ、私はトンボの目の前で指を回しています。捕まえるためではなく、指に乗せるのが好きなのです。うまくいくと、1~3分くらい指先でおとなしく止まっています。
今回ももちろん人がいないので、指を回しました。2回逃げられましたが、3回目に指に止まらせることに成功しました。たばこの煙で即逃げるかと思ったのですが、逃げない。3分近く経っても飛び立とうとしないので、こちらからゆっくり指で払って、飛び立たせました。
以前本で読んだのですが、トンボの目は「複眼」と呼ばれる独特な構造をしています。これは「個眼」という小さな目が集まってできています。トンボの場合は1万個以上の個眼によって複眼が構成されていて、これによって自分を中心にして上下左右前後、約270度の視界を得ていると言われています。この複眼には直線的で速い動きには敏感に反応できるという長所がある反面、ゆっくりとゆらゆら動くものきが非常に苦手という短所があります。目の前で指を回されると、トンボは動いているような物があることを察知できても、はっきりと識別できず、注視することに全力を費やすことになるのだそうです。実際、首を傾げ始めるのですが、このしぐさが実にコミカルで可愛らしい。目が回ったというのではないでしょうが、指を枝か何かと勘違いして警戒もせず指に止まってくれるのです。このトンボさんのおかげでいい休憩が取れ、わずか数分でしたがしみじみと秋を満喫することができました。
トンボは後退せず前にしか飛ばないことから、戦国時代には「勝ち虫」として武将の兜の前立て(兜の前部につける飾り)に用いられました。有名なところでは、加賀百万石の祖・前田利家、徳川四天王の一人の本多忠勝がいます。タイシンの生徒諸君の試験という「戦」を前に縁起の良い虫との出会いでもありました。